本日は3時間20分から3時間10分を切るためのトレーニング。
こういったテーマでお話しします。
みなさま、本日のテーマは「3時間20分から3時間10分を切るためのトレーニングはどうすれば良いか?」というものです。実はこの“3時間20分~10分”というのは、個人的にはかなり重要なテーマだと考えています。
マラソンのタイムという観点で、一つの大きな区切りとしてよく言われるのが「サブ3.5(3時間30分未満)」でしょう。サブ3.5を達成するのも難易度は高いのですが、その次のステップを考えると、サブ3(3時間未満)まではまだ30分という大きな隔たりがあります。
一方、女性ランナーであれば大阪国際女子マラソンの出場資格など、より明確な大きな目標に対しては、やはり3時間台前半でもまだ少し遠いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。サブ3.5を達成した後にも、自分が次にどういった目標を置けばよいのか悩むケースは多いものです。
そこで今回は、「3時間20分を切る」「3時間10分を切る」といったステップアップを意識したトレーニングに焦点を当ててみたいと思います。確実に段階を踏み、目標をクリアしていくという考え方は非常に大切です。ぜひ、一緒に学んでいきましょう。
目次
3時間20分~10分を切るために必要な基礎知識
まず、3時間20分以降の目標設定についておさらいしておきます。
- 3時間20分を切るには、1キロあたりの平均ラップは4分44秒
- 3時間15分を切るには、1キロあたりの平均ラップは4分37秒
- 3時間10分を切るには、1キロあたりの平均ラップは4分30秒
これらの数値は“目安”ではなく“絶対値”になります。大会本番で3時間20分や15分を確実にカットするためには、実際の42.195kmを平均ペースとして上記の時間で走り続けなければいけません。
一方で、練習の際に使うラップ設定や指標となる数値は、あくまでもトレーニングの目安です。例えば、ジャック・ダニエルズさんが提唱する「VDOT」(ブイ・ドット)によると、3時間20分を切るためには10キロのタイムを約43分25秒(平均ラップ4分21秒)で走る力が必要とされています。しかし、これをクリアしたからといって必ずフルマラソンで3時間20分を切れるわけではありませんし、逆にこのタイムに届かなくても3時間20分を切る人もいます。
つまり、「ハーフマラソンや10キロのタイムの目安」はあくまで参考値であり、必ずしも絶対視すべきものではないということを覚えておきましょう。とはいえ、指標がないとトレーニングを進めるうえで目標が立てにくいのも事実です。そのため、“絶対的ではないが、自分の実力をある程度把握できるもの”と割り切って考えることが大切です。
絶対的な指標「レースペース」の重要性
トレーニングの際、多くのランナーにとって唯一と言っていいほど“絶対的なもの”といえるのがレースペースです。これは動かしようのない事実で、「フルマラソンでこのペースを維持しなければならない」という数字になります。よって、自分が目指す目標のレースペースは何分何秒なのかを、まずしっかり把握しておきましょう。
そのうえで、次に意識しておくべきなのが“レースペースの余裕度”です。この“余裕度”という言葉は、厳密な定義はないかもしれませんが、ここでは「レースペースで走ったときに、どれくらいの余裕を感じられるか」という感覚的なものだと捉えてください。
余裕度が高い方が、レース当日にペース維持が楽になりますし、練習自体もスムーズに進められます。しかし、走歴が長くなるほど余裕度が高まるとは限らず、むしろスピードを上げるための伸びしろが少なくなってしまう場合も出てきます。
スピードアップには、VO2MAX(最大酸素摂取量)の強化や、LT値(乳酸性作業閾値)の向上など、高強度のトレーニングが欠かせません。走歴が浅いうちは、ジョギング中心の練習でもスピードが伸びるケースがありますが、ある程度のレベルに達すると、それだけでは限界が見えてくるのです。そのため、走歴が長い方にとって、サブ3.2(3時間20分)やサブ3.1(3時間10分)あたりは、壁を感じやすいゾーンとも言えます。
3時間10分~20分を目指す際に意識したいトレーニングの方向性
では実際、どういったトレーニングを行えば3時間20分や3時間10分を切ることができるのでしょうか。ここでは、**“レースペースに対して余裕度があるタイプ”と、“レースペースに対して余裕度がないタイプ”**に分けて考えてみます。
1.レースペースに対して余裕度が高いタイプ
レースペースに対して余裕度が高いということは、VO2MAXやLT値といった指標を、すでにある程度クリアしている可能性が高いです。つまり、速く走る力は十分に備わっている状態といえます。そうした方がサブ3.2やサブ3.1を狙う場合、必要となる主な課題は42.195kmを走り切るための筋持久力です。いわゆる「脚づくり」ですね。
脚づくりには、ロングランが効果的です。初期の段階ではゆっくり長く走ることでも十分ですが、最終的にはレースペースより15~30秒ほど遅いペースで長い距離を走れるようになると、よりマラソンの特異的なトレーニングとなります。ペースにこだわりすぎるよりも、まずは長時間走ることに慣れ、少しずつペースを上げていくイメージで取り組んでみてください。
ただし、レースが近づく時期になりすぎると、あまりにレースペースに近いロングランを頻繁にやるのは疲労の蓄積やケガのリスクにつながるので注意が必要です。ロングランでの上限ペースは「レースペース+15秒」程度までにとどめ、しっかりと回数を重ねましょう。また、30km走にこだわらず、25kmや35kmなど距離を変えながら実施すると、より効果的に脚づくりを継続できます。
インターバル走やテンポ走は、必ずしも頻度高く行う必要はありませんが、週に1回程度は取り入れることでスピードを維持し、心肺機能の低下を防ぐこともできます。しかし、あくまでメインはロングランやミドル~ロング走での筋持久力強化、というスタンスを忘れないようにしましょう。
2.レースペースに対して余裕度がないタイプ
一方、「3時間20分を切りたいけれど、4分44秒のペースがどう考えてもキツい…」というような、現時点でレースペースに余裕がない方も多いはずです。具体的には、「テンポ走で4分35秒を刻むのが精一杯」「インターバル走が苦痛で、VO2MAXが十分ではない」といった状況ですね。
こうしたケースの場合、まずはレースペースそのものに慣れることが重要になります。本来、オフシーズンであればVO2MAXを高めるために、1000mインターバルや400mインターバルでスピード上限を引き上げるトレーニングに時間を割くのも良いのですが、シーズン中は大会に向けた特異的な練習を優先する必要があります。
そこでおすすめしたいのが、レースペース(もしくは少しだけ速いペース)で10マイル(約16km)~20kmのペース走を繰り返し行うという方法です。例えば、3時間20分を狙う方なら、最初は1キロ4分40秒前後で10マイル走をスタートし、慣れてきたら距離を伸ばしていくか、あるいはペースを少し引き上げていきます。20km程度までペース走を行えば、心肺機能の強化と同時にLT値の向上にもつながるでしょう。
また、この練習を繰り返すと、フルマラソンでのハーフ通過地点がかなり楽に感じられるようになります。いわば“レースペースへの順応”を作ることが狙いです。練習である程度の距離をレースペース以上で走っておけば、本番では自信をもってペースを刻めるはずです。
もちろん、スピード強化が無意味というわけではありません。5kmや10kmでのベストタイムが速ければ速いほど、フルマラソンのレースペースには余裕が出てきます。ただ、スピード強化には長期的な視点が必要で、シーズン真っ最中に慌てて取り組もうとすると、疲労や故障のリスクが高まる可能性があります。オフシーズン(例:4月~夏場)などを活用して、じっくりとスピード能力を底上げするのが理想的です。
具体的なトレーニングメニューの組み方
ここまでのポイントを踏まえると、3時間10分~20分を狙うための大まかなトレーニングメニューは、下記のようなイメージになるでしょう。
- ロングラン(脚づくり)
- 25km~35kmの距離走を定期的に行う。
- ペースは「レースペース+15~30秒」程度まで。
- 距離や時間を確保し、筋持久力を向上させる。
- ペース走(レースペースへの順応)
- 10マイル~20km程度を、レースペースまたはそれより少し速いペースで走る。
- 慣れてきたら距離を伸ばすか、ペースを少し上げる。
- シーズン中は特にここにフォーカスして、フル本番を想定した走力を身につける。
- インターバル走/テンポ走(週1回程度)
- VO2MAXやLT値を下げないために、週1回ほどはスピード系の練習を入れる。
- ただしメイン練習の疲労が溜まっている場合は、無理をしない。
- 調整と休養
- 走り込みと休養のバランスを考え、故障リスクを下げる。
- 疲労が蓄積するほど、高強度の練習は効果が出にくくなるため注意。
これらを繰り返すうえで大切なのは、「自分は今どのタイプか?」を見極めることです。レースペースに十分余裕があるのか、まだ不足があるのか。あるいは長距離を走り切る脚づくりが必要なのか、それとも心肺機能の強化が最優先なのか。ご自身の課題をきちんと理解し、必要な練習を選択していくことが最も重要になります。
数値はあくまで目安。自分の感覚も大切に
最後に改めて強調したいのは、トレーニングメニューの数値(設定ペース)はあくまでも目安であり、“絶対”ではないということです。目安があることで練習の方向性が定まりやすくなり、モチベーションを保ちやすくなるのは確かです。しかし、同じ数値を設定してもそれを楽にこなせる人もいれば、苦手とする人もいます。
トレーニングデータを参考にすることはもちろん大事ですが、自分の体がどう感じているか、心拍数や呼吸がどう変化しているか、そういった感覚的な要素も見逃さずにモニタリングしてみてください。特に故障防止やコンディションの管理には、数値よりも感覚がヒントになるケースが多々あります。
まとめ
- 3時間20分~10分という目標設定は、サブ3に向かううえでも重要なステップであり、女性ランナーにとっても大阪国際女子マラソンなどの大目標を意識する際の通過点となり得る。
- レースペース(絶対値)をまず把握し、次にレースペースに対する“余裕度”を確認する。
- 余裕度が高い方は「脚づくり」重視のロングラン。余裕度が低い方は「ペース順応」重視のペース走を中心に考える。
- インターバルやテンポ走は週1回程度でよいが、オフシーズンにはしっかりスピード強化を積むのが理想。
- トレーニング数値はあくまでも目安であり、最終的には自分の感覚や体調管理を大切にすること。
上記のポイントを参考に、ぜひ今後の練習計画を立ててみてください。しっかりと目標をクリアしていくためには、まずは自分の課題を正しく把握することが肝心です。そして、練習メニューを組み立てる際には、常に「今自分は何を伸ばしたいのか」を意識して取り組むと、より効率的に力をつけることができます。ぜひ、日々のトレーニングに活かしていただき、皆さんが3時間20分や3時間10分を切れるよう応援しています!
こちらのブログの内容を動画で学びたい方はこちらからご覧ください。





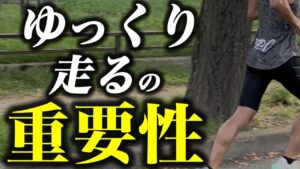

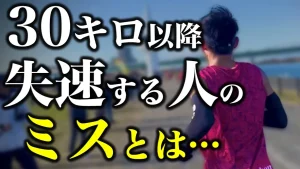
コメント