フルマラソンの大本命レースがいよいよ間近に迫り、多くのランナーが最終調整を行っていることでしょう。フルマラソンを攻略するうえで最も重要なのは、後半、特に30キロや35キロ以降の失速を防ぐことです。これを避けるために、日々厳しいトレーニングを積んでいる方も多いはず。
今回は、そんな30キロ以降の失速を防ぐために、レース直前でも実践できるポイントを徹底解説します。これからご紹介する内容は、正直言って新しい発見というよりは「わかっているけど徹底できていない」というものかもしれません。しかし、これを押さえるかどうかで、後半のペースダウンを大きく防げる可能性があります。最後までしっかり読んでくださいね。
目次
30キロ以降の失速を防ぐための2つの直前対策
1. オーバーペースのコントロール
レース序盤にペースを上げすぎると、後半に必ずツケが回ってきます。特に市民ランナーの多くは、後半落ちることを想定して「少しでも前半に貯金を作りたい」と考えがち。しかし、前半でオーバーペースになると、30キロ以降の大失速を招く原因となります。
オーバーペース対策の一例
- 突っ込む距離を決める: 例えば最初の10キロまでは少し速めに入って良いが、それ以降はレースペースに落ち着かせる。
- 上限ペース(ボーダーライン)を決める: サブ3.5(3時間30分切り)を狙う場合、平均ペースは1キロ4分58秒程度。この場合「4分53秒より速く走らない」といった明確なルールを自分に課す。
実際、筆者自身も先日開催された別府大分毎日マラソンでこの方法を使い、PB(自己ベスト)を更新しました。調子がいいと、ついペースを上げてしまいがちですが、あらかじめ上限を決めておくことで大失速を防ぎやすくなります。
2. エネルギー補給の適切な管理
フルマラソンでは、約2,500〜3,000kcalを消費すると言われていますが、体内のグリコーゲン量はおよそ1,600kcal程度です。つまり、そのまま走り続けるとエネルギーが不足し、30キロ以降に失速するリスクが高くなります。
また、近年の研究では「低血糖」がパフォーマンス低下の主要因のひとつであると示唆されています。レース中の補給では、糖質を中心に血糖値を安定させることが鍵となります。
エネルギージェルを選ぶポイント
- 十分な糖質が含まれていること
- 自分の口に合うもの(味やテクスチャーなど)
有名どころでは、アクティバイク(糖質バランスが良い)、マグオン(マグネシウム豊富で足つりにも有効)、ウィンゾーン(評判が高い)などがよく名前の挙がるジェルです。どんなに“良い”と言われているジェルでも、口に合わないと使い続けられないので、試飲・試食をして自分に合ったものを選びましょう。
30キロ以降の失速の主な原因を再確認
「失速を防ぐための基本はオーバーペースを避け、エネルギー補給を怠らないこと」ですが、そもそも30キロ以降に失速する原因は、下記3つに大別できます。
1. エネルギー枯渇と低血糖
昔から、30キロ以降の“ガス欠”はグリコーゲンの枯渇が主因とされてきました。しかし近年は、単なるエネルギー不足だけでなく、低血糖が脳に与える影響が深刻であると分かっています。脳のエネルギー源である糖質が不足すると、体が動かなくなるだけでなく、集中力や判断力も落ちるため、ペースダウンが顕著に現れます。
2. 筋疲労と乳酸蓄積
長時間の運動により筋肉に乳酸が蓄積すると、筋収縮力や持久力が低下します。レース後半、足が重くなり思うように動かなくなるのは、乳酸の蓄積に加え、筋損傷が重なって発生する疲労現象でもあります。特にロング走などの経験が少ないと、この症状が顕著に出やすいです。
3. 神経筋疲労と中枢性疲労
身体が疲れるだけでなく、脳も疲弊してしまう状態です。神経から筋肉への伝達効率が低下して筋肉が動きにくくなったり、脳が“これ以上走らないで”と指令を出して運動を抑制する中枢性疲労が起きたりします。これはエネルギー不足、精神的ストレス、睡眠不足など、様々な要因が複合的に絡むものです。
これら3つの原因は相互に関連しており、一つが極端に悪化すると他の要因も引き起こしやすくなります。したがって、複数の対策を組み合わせることが重要です。
長期的に考えるべきポイント
ここからは、直前ではなく中長期的に行うことで30キロ以降の失速を予防する対策をご紹介します。今回のレース直前には間に合わないかもしれませんが、今後フルマラソンに挑む方は、ぜひ参考にしてみてください。
1. トレーニング方法の見直し
- LT(乳酸性作業閾値)走: 乳酸が溜まり始めるペースでのトレーニングを行うことで、乳酸を処理する能力が高まり、より速いペースを持続できます。LT走は週に1回程度組み込むのが目安です。
- 30km以上のロング走: 実際に長い距離を走り、筋持久力や精神的持久力を鍛えます。初心者は月に1回、上級者はもう少し頻度を上げるなど、自分のレベルに合わせて取り入れましょう。
- 脂質代謝の向上: MCTオイル(中鎖脂肪酸)などを取り入れることで、体脂肪をエネルギー源として活用しやすくし、糖質の消費を抑える手法も注目されています。ただし、日常的な摂取やトレーニング時の実践が必要なため、直前だけでは効果を発揮しにくい点に注意しましょう。空腹状態での運動が有効です。朝起きて、水だけを飲み30分のウォーキングやジョグを習慣づけるのも、いいでしょう。
2. ペース配分の工夫
レース当日のペース配分は、失速を防ぐために極めて重要です。理想は
- ネガティブスプリット(後半ペースアップ)
- イーブンペース(ほぼ一定のペース)
車の燃費に例えると分かる通り、アクセル(ペースアップ)とブレーキ(ペースダウン)を繰り返すとエネルギー効率が悪くなります。一定のペースを刻む“イーブンペース”が理想的とされる理由がここにあります。
とはいえ、後半に大きくペースを上げられるほど余裕があるランナーは限られています。そこで**“ほぼイーブンに近いポジティブスプリット”**で走ることも選択肢の一つ。具体的には、前半と後半のハーフのタイム差を1分程度に抑えるイメージです。
たとえば、前半ハーフをギリギリ攻めても後半が1分落ちるだけで済めば、全体としては大崩れを回避できます。前半の突っ込みすぎは要注意ですが、どうしても攻めたい方は先ほどお伝えしたような“突っ込む距離を限定する方法”を試してみてください。
レース直前にやっておくべき準備
- 疲労抜き: トレーニングのしすぎで疲労が蓄積したまま本番を迎えると、脚が重くなるだけでなく、精神的にも不安になります。レース1〜2週間前は、距離と強度を落として体を回復させる期間を作りましょう。
- 補給食やジェルの最終確認: レース本番で初めて口にするジェルは失敗のもとです。事前に試しておいて、当日の胃腸トラブルを防ぎます。
- ペースのシミュレーション: 目標タイムに対して、1キロあたり何秒で走るかをはっきり決め、それを超えそうになったら落とす、といったルールをシミュレーションしておきましょう。
まとめ
30キロ以降の失速を防ぐために、まず直前対策としてオーバーペースを抑え、適切なエネルギー補給を行うことを徹底してください。そして中長期的には、LT走やロング走で持久力をつける、脂質代謝を高めるトレーニングを取り入れるなど、失速を根本的に防ぐ準備が必要です。
市民ランナーにとって、後半ペースダウンは決して珍しいことではありません。しかし、「どうせ落ちるから前半で貯金を作る」という発想は危険です。むしろ、一定ペースで走り切ることが体にとってもエネルギー効率的にもベストだと考えてください。もしどうしても突っ込みたい場合も距離を区切る、ペースの上限を決めるなどの工夫をし、後半に備える形を取るとよいでしょう。
レース本番が近づくと、誰しも不安になりますが、焦って過度な練習をしてしまうとかえって疲労が抜けません。本番数日前はできるだけ体を休め、当日は万全の体調でスタートラインに立つことが最重要です。
最後まで準備を抜かりなく、そしてレースも最後まで諦めずに走り切りましょう。練習の成果を最大限に発揮し、30キロ以降の失速を防いで、大本命のレースを充実したものにしてください。
皆様の健闘を心から祈っています!
動画で学びたい方はこちらから

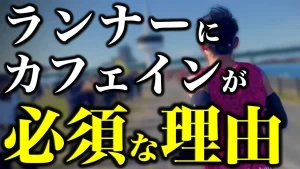

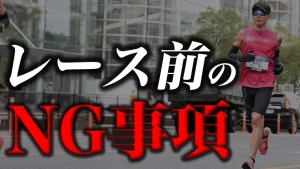
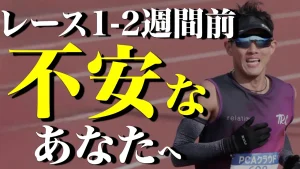
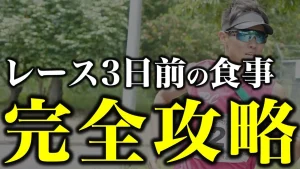
コメント