今回は「ジョギング練習を距離で管理するか、それとも時間で管理するか?」というテーマでお話していきます。
これは私自身、日々のトレーニングで常に意識しているポイントでもありますし、多くのランナーの方が疑問に思うところでもあるのではないでしょうか?
ぜひ最後までご覧いただき、参考にしていただければ嬉しいです。
冒頭でもお伝えした「マラソンのジョギング練習は“距離”か“時間”どちらで管理するのがいいのか?」という考え。
結論から言いますと、“距離がいい”“時間がいい”という絶対的な正解はありません。
それぞれにメリット・デメリットがありますし、目的やライフスタイルに応じて使い分けるのが大切です。
- 「距離で走る」ことで得られるメリットと、その際に気をつけたいデメリット
- 「時間で走る」ことで得られるメリットと、その際に気をつけたいデメリット
- そして、マラソンにおいて重要なロング走を行うときの注意点
こうしたポイントを押さえながら、自分に合った練習スタイルを見つけるヒントをお伝えしていきます。
目次
▼距離で走る特徴
まずは「距離管理で走る」メリット・特徴について詳しく見ていきましょう。
1. 目標を決めやすい
距離を設定する最大のメリットは、ゴールが明確なことです。
「あそこまで行けば○km」「このコースを何周走れば○km」といった具合に走る場所や周回数が明確になるので、目標地点がはっきりします。
たとえば、10km走ると決めれば、その10kmを達成するまではしっかり走りきるという意識が働きやすいため、モチベーションを保つのにも役立ちます。
特に決まった周回コースやランニング専用のトラック、河川敷コースなどが近くにある方は、「今日は○周」という形で管理がしやすいですよね。
2. 後半にかけてペースが上がりやすい
距離走では、ゴールまでの残り距離がはっきりとわかるので、心理的に「もう少しで終わる!」という気持ちが働きます。
そのため、後半にペースが上がりがちです。
ランナーとしては「自然とペースが上がるのは良いことでは?」と思うかもしれませんが、気をつけたいのは無理に上げすぎないこと。
あくまで自然に体が動いてペースが上がる(余裕を持ってビルドアップできる)ことが理想です。
急激なペースアップを狙うと、疲労が急激に溜まってケガにつながるリスクもあります。
特に初心者や怪我明けのランナーは、無理をしないように注意しましょう。
3. レース距離を明確に意識できる
フルマラソンでは42.195kmという距離があります。
たとえば「今日はレースの3/4である30km走をやる」「35km走に挑戦して、脚づくりをしたい」といったように、具体的な距離を目標として設定しやすいのも距離管理の特徴です。
後でお話しするロング走のポイントとも関連しますが、レースの距離に対する不安を徐々に減らしていくには、有効な練習方法です。
一方で距離管理で注意したいのは、ペースに関しての縛りがゆるいため、知らず知らずのうちにオーバーペースになりやすい側面がある点です。
ある程度の距離を走りきろうとして、前半から飛ばしすぎると後半バテてしまう、といった経験をされた方も多いと思います。
距離を決めて走る場合は、「走る距離+目安となるペース」をあらかじめ設定しておくと、無理なく一定の負荷で走りきりやすくなります。
▼時間で走る特徴
続いて「時間管理で走る」方法のメリット・特徴を確認してみましょう。
1. 終わる時間がわかりやすい
時間管理のメリットは、なんといっても「○分後に終わる」「○時まで走る」という終わりの明確さです。
市民ランナーの多くは、仕事や家事・育児といった本業があり、その合間をぬってトレーニングをします。
決められた時間枠のなかで、練習を無理なくスケジュール化しやすいのは大きな魅力です。
たとえば朝に30分時間が取れれば30分走、休日に1時間確保できれば1時間走、といった形で柔軟にアレンジできます。
ライフスタイルに合わせてコンスタントに走り続けやすいのです。
2. ペースが一定に保ちやすい
距離管理だと「速く走れば早く終わる」ため、どうしてもペースが乱高下しがちです。
しかし時間管理だと、速く走っても終わる時刻は変わりません。
したがって「巡行ペース」を見つけやすく、一定のペースを淡々と刻むトレーニングには最適です。
特にフルマラソンは長時間の運動になるため、ペースを安定させてエネルギーロスをできるだけ抑えることが重要です。
時間走を継続して行うことで、「省エネで長く走り続ける走り方」の習得に近づけるのは大きな強みと言えるでしょう。
3. 感覚的に強度をコントロールしやすい
時間管理の場合、「今日は少し体が重いからペースはゆったり」「今日は調子がいいから同じ時間内でちょっとペースを上げる」といった、走りながら調整しやすい感覚があります。
たとえば60分間走ると決めておけば、無理なく自分の調子に合わせてペース配分ができます。
距離を決めてしまうとどうしても「あと○km残っているから頑張らないと…」と無理にペースを維持してしまい、疲労感が蓄積する可能性が高まることも。
ケガやオーバーワークを防ぐ意味でも、時間管理は柔軟性があるといえます。
ただし時間管理には、「このくらいの時間で走っていれば、だいたい走力が上がるだろう」という感覚的な部分が強いというデメリットもあります。
距離設定のように明確に積み上げていく目安がややぼんやりしがちなので、ペースアップや距離の伸びがどの程度なのか分かりにくい場合もあるでしょう。
そこで、タイムだけでなく「走った距離や平均ペース」を記録しておき、「1時間走で前回は何km走れた」「最近は同じ1時間でも走れる距離が増えた」という形で客観的に進捗を確認する工夫をすることも大事です。
▼ロング走をする時の注意
ここからは、フルマラソンに向けた練習で欠かせない「ロング走」をする際の注意点について、距離管理と時間管理の両面から考えてみます。
1. 時間走で行うロング走
フルマラソンでは、レースの目標タイムを意識して走ることが非常に大切です。
たとえば「4時間切りを目指している人なら、実際に3〜4時間近く動き続ける練習をしたい」というように、目標レース時間を意識して身体を慣らすことが効果的とされています。
ただし、3時間以上走るとなると、初心者や中級者の多くにとってはかなり高い強度の練習となります。
無理を重ねると筋肉や関節への負荷が大きくなり、故障につながりやすいです。
そこで方法として、たとえば週末に2日連続で90分ずつ走る、もしくは同じ日に朝と夕方に分割して走る「二部練」という形で合計2〜3時間程度の走行時間を確保するやり方があります。
こうすると身体を追い込みすぎず、翌日の生活にも支障を出しにくくなります。
目標タイムを意識した時間走は、実戦感覚を養いつつもオーバートレーニングを防ぐよう工夫するのが肝心です。
2. 距離走で行うロング走
もう一方で、距離管理のロング走は「レース距離を想定した段階的な距離アップ」がポイントです。
たとえば最終的に42.195kmを走りきるために、「まずは20km」「次に25km」「30km」「35km」というように、徐々に距離を伸ばしていきます。
特に30kmの壁や35kmからの失速といったマラソン特有の課題に慣れるためには、一定の長距離を踏んで慣れさせておく必要があるという考え方です。
ただし、やみくもに長い距離を走れば良いというわけではありません。
レースまでに十分な準備をするためには、以下のような要素を組み合わせることが重要です。
- 設定ペース:自分の目標ペースや現状の走力を踏まえて、適切なペースで走る。
- 段階的な負荷調整:一気に30kmや35kmに挑戦せず、段階を踏んで距離を伸ばす。
- 休養とのバランス:長距離を走った後はしっかりと休養をとり、筋肉や関節の回復を図る。
オーバーワークを避けるためにも、ロング走は計画的に行う必要があります。
また、長距離を走る際は水分・栄養補給が欠かせません。
特に夏場の暑い時期や寒い時期の給水タイミングなど、安全面にも気を配りながら行いましょう。
3. どちらにしろ段階的に行うのが重要
時間走であれ距離走であれ、ロング走は段階的に行わないと身体への負荷が急増し、ケガに直結するリスクがあります。
オーバーワークになると、せっかく継続してきたトレーニングを中断しなければならなくなるため、長期的に見たトレーニング効果が下がってしまいます。
特に初心者や、自己ベストを更新したい中級者でも、高負荷の練習を連続で行うのは危険です。
練習量を増やすときは「走る距離を徐々に伸ばす」のか「走る時間を少しずつ長くする」のか、いずれかの方法をとりつつ、体調と相談しながら無理のないステップアップを図りましょう。
▼まとめ
いかがでしたでしょうか。「距離で走る」と「時間で走る」、どちらの方法にも一長一短があります。
主に以下の点を押さえて、ぜひ日々のトレーニングに活かしていただければと思います。
- 距離管理:ゴールが明確でモチベーションを保ちやすい。後半ビルドアップしやすいが、無理にペースアップするとケガにつながる恐れあり。レースの距離を想定したロング走を組みやすい。
- 時間管理:終わる時間がはっきりしていて、忙しい社会人や主婦・主夫ランナーにとってスケジュールに組み込みやすい。一定ペースを刻む練習に適し、省エネ走法を身につけやすいが、距離の伸びがわかりにくいので記録をつける工夫が必要。
ロング走については、時間で行うか距離で行うかはあなたの目標次第です。
レース時間を想定して3〜4時間動き続けることを意識したい方は時間走が有効ですし、レース距離に慣れたい方や脚づくりを重視する方は30kmや35km、あるいは40kmといった距離を設定する練習が効果的です。
ただし、どちらの場合も負荷が大きいので、オーバーワークを防ぐために分割練習や休養の徹底などが求められます。
最終的には「自分に合った方法」「自分のライフスタイルにマッチした方法」を探ることが大切です。
仕事や家庭の事情、個々の体力レベル、走る目的(レース完走や自己ベスト更新など)に応じて、距離管理と時間管理を上手に使い分けてください。
たとえば平日は短時間で効率よく時間走を行い、週末に余裕があるときには距離走でしっかり負荷をかける、といった形でメリハリをつけるのもおすすめです。
今日は、「距離で管理するか」「時間で管理するか」というテーマで、両方の特徴とロング走の注意点について詳しくお話ししました。
これからフルマラソンを目指したい、あるいは自己ベストを更新したい方にとっては、練習方法を再点検するいいきっかけになれば嬉しいです。
どちらも長所・短所がありますので、うまく使い分けながら自分に最適な練習計画を作ってください。
動画で学びたい方はこちらから





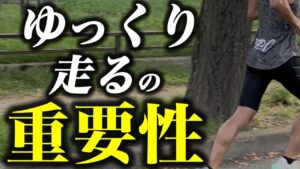

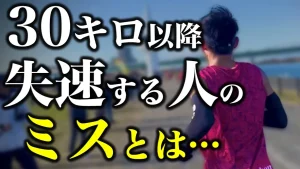
コメント