目次
【はじめに】
マラソンのレースシーズンは、秋から春にかけて各地で開催されることが多く、とりわけ3月頃にメインレースを終えるランナーは少なくありません。陸上競技の世界では4月からが新シーズンとなり、2024–2025シーズンも3月で一区切りを迎えます。本稿では、この時期を「休養期」と位置づけることの意義や、具体的な過ごし方について解説します。
「3月に休養期を設けるべきかどうか」は人によって意見が異なりますが、シーズンを通してパフォーマンスを高め続けるためには、トレーニングと休養のバランスが必要不可欠といえるでしょう。
【1. 3月の休養期とは】
一般的に「3月は休養期」といわれますが、本来はレース終了後の1〜2週間、長くても1ヶ月程度を指します。12月に大きな大会を走る方であれば、大会後に一度休養を取り、トレーニングを再開して春に備えるのが自然な流れといえます。
市民ランナーの多くは、12月にピークを迎えたあと軽い休養を挟み、3月のシーズンラストレースが終わった段階でまとめて休養期を取り、心身をリセットするケースが多いのではないでしょうか。年末年始は生活リズムが変わりやすく、秋からのレースで蓄積した疲れが抜けきらないままトレーニングを続けてしまい、コンディションを落とす可能性があります。
このため、3月のレースを終えた後にはしっかり休養を取ることで、身体とメンタルの両面をリフレッシュすることが推奨されます。
【2. 休養期の目的】
休養期の最大の目的は、秋から冬にかけて行われた高負荷トレーニングで蓄積した疲労を抜くことです。距離走やスピード練習などを行ったうえでレース本番を迎えると、筋肉や関節、免疫系、神経系、ホルモン系に至るまで全身に疲労が溜まります。
加えて、長期間にわたる精神的ストレスが原因で「燃え尽き症候群」が発生するリスクも高まります。燃え尽き症候群は単なるモチベーション低下だけでなく、免疫系や神経系、ホルモンバランスの崩れによっても引き起こされる可能性があり、身体的・生理的要因が重なって深刻化するケースがあります。こうした状態を防ぐためにも、休養をしっかり取り、これらの機能を回復させることが重要といえるでしょう。
「少しくらいのやる気低下」で済む段階であれば早期に修正が可能ですが、症状が重くなるとトレーニングに復帰しにくくなる場合があります。休養期は、次のシーズンへ向けて身体的・精神的に回復・充電をする期間として捉え、積極的に設けることをおすすめします。
【3. 休養期は本当に必要か】
「休養期など不要」という声も一部では聞かれますが、トレーニングを長期的に続けるうえで休養をまったく取らない場合、疲労が抜け切らないまま故障や燃え尽き症候群を招くリスクが高まります。一方で、「まったく休養を取らない方がコンディションを落とさずに済む」と考える方もいるかもしれません。
しかし、しっかりトレーニングを積んだ後に計画的な休養を取ることで、モチベーションを維持しやすくなり、身体的にも回復の時間を確保できます。また、休養期には今シーズンを振り返って課題を洗い出し、次のシーズンに向けた目標やトレーニング計画を策定することで、再開後のトレーニングをスムーズに進めやすくなるメリットもあります。
ただし、休養期間が長すぎると再開時のハードルが上がり、身体が鈍ってしまう恐れがあります。完全に体を動かさないというよりは、軽いジョグやクロストレーニングなど、負荷を抑えながら適度に体調を維持することが望ましいでしょう。
【4. 休養期の過ごし方(トレーニング編)】
休養期の運動内容は、低強度・短時間を基本とするのがおすすめです。以下のような方法を取り入れると、疲労を増やさずに体を動かすことができます。
- ジョギング(低強度走)
3〜60分程度の軽いジョグは、完全に走らない日を作るよりもコンディションを保ちやすくなります。疲労を増やさない程度に走ると、ストレス発散にもつながるでしょう。 - クロストレーニング
プールやヨガ、自転車など、ランニングとは異なる動作で心肺機能を刺激しながら足を休ませる方法です。筋肉や関節への負荷を抑えつつ、運動習慣を途切れさせない利点があります。 - ランニングマシンの活用
室外の路面を走るより衝撃が少なく、関節への負担をコントロールしやすいのが特徴です。傾斜や速度を自由に調整できるため、疲労度に合わせた運動が可能です。 - 高強度練習の制限
インターバル走やビルドアップ走など高負荷のメニューは、休養期には極力控えましょう。疲労を抜く期間であることを再認識し、過度な負荷をかけないよう心掛けることが大切です。
【5. 休養期の過ごし方(食事編)】
休養期は運動量が減るため、摂取エネルギーが過多になると体重増加や体調不良の原因にもなりかねません。と同時に、体内の炎症を抑え、回復を促進する期間でもあるため、以下の点に留意すると良いでしょう。
- 炎症を起こしやすい食事に注意
- 加工食品(加工肉、スナック菓子など)
- 高脂質のファストフード
- トランス脂肪酸を多く含む食品(マーガリン、ショートニング、揚げ物など)
- 砂糖や精製炭水化物(甘いお菓子、清涼飲料水など)
- サラダ油やコーン油
- アルコールの過剰摂取 これらを習慣的に大量摂取すると、体内で炎症が起こりやすくなるリスクがあります。
- 炎症を抑える食事を積極的に取り入れる
- 野菜・果物
- 青魚
- エゴマ油、アマニ油
- 発酵食品(納豆、ヨーグルト、キムチなど) 休養期の間にこれらの食材をバランスよく摂取すると、身体の回復力をサポートできます。とはいえ、好きなものを完全に断つ必要はありません。ご褒美的な食事も楽しみながら、全体的な栄養バランスを意識することが望ましいでしょう。
【6. 休養期が明けた後の準備】
休養期が終わったら、できるだけスムーズにトレーニングを再開できるよう、振り返りと計画立案を行います。
- シーズンの振り返り
どのレースでどの程度走れたのか、どのタイミングで課題が生じたのかを再確認します。練習日誌やレース直後の記録が残っていれば、改めて見返すと良いでしょう。 - 目標設定
次のシーズンで狙うタイムや、どのような走りを目指すのかを明確にします。あまりにも高すぎる目標よりも、達成可能な範囲で少し背伸びをする目標のほうがモチベーションを維持しやすいものです。 - トレーニング計画の策定
いきなり高負荷のメニューに戻すと故障リスクが高まります。徐々にボリュームや強度を上げていくスケジュールを組みましょう。コーチやトレーニング仲間がいる場合は、相談しながら計画を練ることをおすすめします。
【まとめ】
休養期は、シーズンを通してトレーニングを行った結果、心身に溜まった疲労を回復し、次のシーズンに向けてリセットするための大切な期間です。適切な休養を挟まず走り続けると、故障のリスクや燃え尽き症候群に陥る可能性が高まります。
- レース後1〜2週間、最長1ヶ月程度を休養の目安とする
- 低強度の運動やクロストレーニングで体を動かしつつ、強度の高いメニューは極力避ける
- 暴飲暴食を控え、炎症を抑える食材を意識的に摂取する
- シーズンの振り返りと次の目標、トレーニング計画を立てて、新シーズンに備える
これらを踏まえ、休養期を上手に活用することで、より高いレベルのパフォーマンスを目指せるようになるはずです。長期的にマラソンを楽しみながら記録更新や健康維持を続けるためにも、休養とトレーニングのバランスを大切に取り組んでみてください。





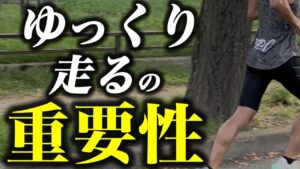


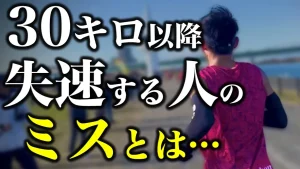
コメント