目次
走行距離を伸ばす上で注意してほしいこと
挨拶
今回は「走行距離を伸ばす上で注意してほしいこと」というテーマでお話ししていきたいと思います。ランニングをしている方なら、「もっと走行距離を伸ばして強くなりたい!」と考えることがあるのではないでしょうか。
しかし、ただ闇雲に走行距離を伸ばしてしまうと、怪我やパフォーマンス低下につながるリスクが高まります。例えば、急に長時間走る習慣を取り入れると、足首や膝などの関節に過度な負担がかかり、思わぬ故障につながるケースも少なくありません。
そこで今回は、走行距離を上手に伸ばすための方法や、伸ばす際に注意してほしいことを具体的に解説していきます。練習は継続してこそ効果が出るもの。正しい知識を身につけて、一緒にランニングライフをより充実させていきましょう。
動画(記事)のテーマ
本日のテーマは「走行距離の伸ばし方」と「その際に気をつけるポイント」です。
走行距離を増やすメリットは多々ありますが、一方でやり方を間違えると怪我や疲労の蓄積から走れなくなってしまうケースも見られます。そうなると、せっかく積み上げた基礎体力やモチベーションを失うだけでなく、回復にも時間がかかり、長期的に見ると非常にもったいないですよね。
ランニングは続けること自体に大きな意味があります。多くのランナーが抱える悩みのひとつが「怪我でしばらく走れなくなる」といった事態ですが、これを防ぐためにも、距離の伸ばし方とトレーニング全体のバランスをしっかり押さえることが大切です。また、着実に走行距離を増やすことで、ゆくゆくはフルマラソンやウルトラマラソンなど、さらなる挑戦への自信にもつながっていきます。
走行距離を伸ばすメリット
まずは、走行距離を伸ばすと具体的にどのような良い影響があるのかを再確認しておきましょう。大きく分けて、以下の3点が挙げられます。
1. 疲労回復力の向上
走行距離が増えることで、疲労回復能力がアップします。要因としては大きく2つあると考えられます。
1)毛細血管の増加
走行距離を増やすと、体内の毛細血管の数が徐々に増えていきます。髪の毛ほど細い血管ですが、トレーニングを重ねることで発達し、全身の隅々に酸素や栄養が届けられやすくなるのです。
血管網が拡大すると、老廃物や疲労物質の排出もスムーズになり、翌日の練習でも体が重くなりにくくなります。
2)ミトコンドリアの増加
ミトコンドリアは「エネルギー生産工場」と呼ばれ、運動量が増えるほど増加していきます。ミトコンドリアの数が多いほど効率よくエネルギーを作り出せるため、後半のスタミナ不足が減り、結果的に疲労回復も早まります。
2. 筋肉、関節、腱、靱帯の強化
ランニングは片足接地の連続、いわば「連続ジャンプ」のような動作です。
この動作を繰り返すことで、下半身の筋肉や腱・靱帯が強化され、スピードを出した際も効率的に走ることが可能になります。さらに筋力が上がれば、RE(ランニングエコノミー)の向上にもつながり、長く走れるうえにペースアップもしやすくなるというメリットがあります。
また、筋肉や腱・靱帯が強化されることで怪我の予防にも繋がります。ランナーにとって故障は大敵ですが、定期的に走行距離を増やしながら足回りを鍛えることで、多少の負荷でも耐えられる強い身体に近づくでしょう。
3. 練習の積み上げやすさ向上
走行距離を伸ばすことで、疲労回復力や筋力が高まり、より質の高い練習を取り入れやすくなります。ある程度走り込んだ体であれば、インターバル走やビルドアップ走といった負荷の高いトレーニングを行っても、翌日以降の回復が早くなり、次の練習にスムーズに移行できる可能性が高まります。
私の周囲でも「距離を増やしたら速いペースを維持できるようになった」「疲労が溜まりにくくなった」という声が多く聞かれます。私自身も昨シーズンに比べて月間走行距離を100キロほど増やしましたが、怪我をせず、筋肉の張りや違和感が減りました。後半まで余力を残せるようになり、レースでの自己ベスト更新にも大いに役立ちました。
走行距離を伸ばすときに注意してほしいこと
ここからは、走行距離を伸ばすときに必ず押さえておきたいポイントを3つ紹介します。急激な距離の増加は、オーバーワークや疲労骨折など予期せぬトラブルにつながるため十分に注意してください。
1. 慎重に伸ばす
「走行距離を伸ばせば良いことばかり!」と思って、一気に増やすのは非常に危険です。
月間100キロを走っている方が、いきなり月間1000キロを走るなどの極端な増やし方をすれば、間違いなく故障に直結するでしょう。初心者ランナーほど頑張りすぎる傾向があるので、特に注意が必要です。
トレーニングは週ごとのサイクルで管理する方が多いので、「週間走行距離を5~10%ずつ増やす」という目安を持ちましょう。週50キロ走る方なら、翌週は52.5キロ、さらに翌週は55キロ前後…というように少しずつ増やしていきます。1週間では僅かに思えても、長い目で見ると着実に走力がつき、怪我のリスクも抑えられます。
2. 筋力強化を同時に行う
走行距離を伸ばすということは、それだけ足回りの負荷が増えるということ。筋力が不足した状態で距離だけ増やしても、フォームが崩れやすくなり、怪我の原因にもなります。
そこで欠かせないのが筋力トレーニング。スクワットやデッドリフトなど、ある程度の負荷を扱うトレーニングを行うことで、
- 地面を押す力の強化
- 体幹や下半身の安定
- 疲労蓄積の軽減
などが期待できます。最大筋力を求めるような極端な重量トレーニングまでは必要ありませんが、適度な重さを扱って筋力を伸ばすことは、ランナーにとって大きな武器になるでしょう。
3. メンテナンスの量を増やす
走行距離を増やすほど、身体には大きなストレスがかかります。そのため、回復作業やメンテナンスを充実させないと、疲労が抜けきらないまま次の練習に移り、怪我や体調不良を引き起こしやすくなります。
特に意識してほしいポイントとして、
- ストレッチやセルフマッサージで筋肉の柔軟性を保つ
- 入浴で身体をしっかり温め、血流を促す
- バランスの良い食事やサプリメントの活用
- シューズの状態チェックや必要に応じた交換
- 同じ部分に痛みがある場合はフォームの見直しや専門家への相談
などが挙げられます。走るだけでなく、回復や補強を徹底することが、長期的に走行距離を伸ばし続けるカギになります。
まとめ
走行距離は、ランナーのパフォーマンス向上にとって重要な要素です。正しいペースで伸ばせば、疲労回復力や筋力の強化、RE(ランニングエコノミー)の改善など、多くのメリットを得られるでしょう。
ただし、無理をしてオーバーワークに陥ると、走れない期間ができてしまい、せっかくのトレーニングが台無しになるリスクもあります。市民ランナーの方であれば、家族や仕事との両立も大切です。走行距離を増やすあまりプライベートを圧迫しすぎないように気をつけてください。
まずは月間200キロなど、無理のない範囲で目標を設定し、週あたり5~10%ずつ少しずつ距離を増やしていきましょう。並行して筋トレを取り入れ、回復をしっかり行う。これらを意識すれば、怪我のリスクを抑えつつ走力を着実に向上させられるはずです。
ぜひ、自分の体調や生活パターンと相談しながら、計画的に走行距離を伸ばしてみてください。そうすることで、ランニングライフを長く、より充実したものにしていけるでしょう。




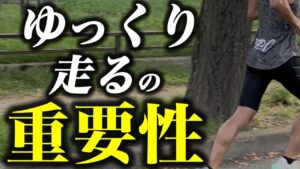


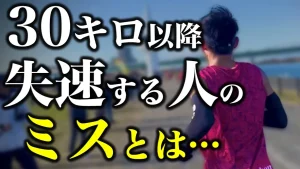
コメント