今回は、「ランナーとアルコールの関係性」についてお話しします。ランニングを趣味として楽しんでいる方、あるいは本格的に取り組んでいる方も、日々の生活の中でお酒を飲む機会があると思います。そこで気になるのが、「お酒を飲むことは、ランニングのパフォーマンスや健康にどのような影響を与えるのか?」という点ではないでしょうか。
本日は、以下の内容を軸に進めていきます。
- お酒が身体に与える影響
- お酒が運動に与える影響
- お酒がランナーに与える影響
- メリットとデメリット
- ランナーのアルコールとの付き合い方(結論)
それぞれ、エビデンスも交えてお伝えいたします。ぜひ最後までご覧ください。
目次
2. お酒が身体に与える影響
2-1. アルコールの吸収・代謝の流れ
まず、アルコールがお身体に入ったときの基本的なメカニズムから確認しましょう。
- 吸収: アルコールは口から飲むと、胃や小腸で吸収されます。吸収されたアルコールは血管を通じて全身へと運ばれていきます。
- 代謝: 体内に入ったアルコールの大部分は肝臓で分解されます。酵素(アルコール脱水素酵素やアセトアルデヒド脱水素酵素)によって段階的に分解され、最終的には水と二酸化炭素などに変えられます。しかし、肝臓の処理能力を超える量のアルコールを摂取すると、血中アルコール濃度が高まり、さまざまな悪影響が出てきます。
2-2. 中枢神経への影響
「中枢神経」とは、私たちの身体の司令塔となる神経系統で、具体的には「脳」と「脊髄」が含まれます。アルコールは、この中枢神経を抑制する働きがあります。
- 少量の場合: リラックス効果や気分の高揚をもたらすことがある一方、すでに疲労が溜まっている時には眠気を増したり、判断力を鈍らせたりします。
- 大量の場合: 意識レベルが低下し、酔いつぶれる、平衡感覚が失われるなどの症状が起きやすくなります。
2-3. 脱水作用
アルコールには利尿作用があります。利尿作用とは、体内の水分を排出する方向に働く作用のことを指します。そのため、飲酒後はトイレに行く回数が増え、水分不足(脱水状態)になりやすいのです。脱水状態になると血液の量が減ってしまい、結果として筋肉への酸素供給や栄養供給に影響が出る恐れがあります。
2-4. 肝臓や心血管系への負担
アルコールを長期にわたって大量に摂取すると、肝臓機能が低下しやすくなることは広く知られています。また血圧が上昇しやすくなり、循環器系のリスク(心筋梗塞や脳卒中など)も高まります。これは一般の人だけでなく、普段から運動をしているランナーも例外ではありません。健康あってのランニングですから、この点はとても重要です。
3. お酒が運動に与える影響
次に、お酒が運動全般に与える影響について見ていきましょう。ここでは、トレーニングやパフォーマンスという観点から、主なポイントを解説します。
3-1. 筋タンパク合成の阻害
筋力や持久力を向上させるためには、筋肉の修復と成長が不可欠です。そのプロセスには、「筋タンパク合成」という反応が重要な役割を果たします。ところが、アルコールを過剰に摂取すると、この筋タンパク合成が抑制される可能性があると報告されています(参考: Journal of Strength and Conditioning Research)。
- 特に問題になるタイミング: 運動直後や就寝前などは、筋肉が修復・合成を活発に行う“回復のゴールデンタイム”です。このタイミングで大量のアルコールを摂ると、せっかくの回復・成長を妨げるリスクがあります。
3-2. エネルギー供給への影響(グリコーゲンの枯渇)
ランニングなどの有酸素運動時には、主に体内のグリコーゲン(糖質が貯蔵されたもの)と脂肪がエネルギー源として使われます。アルコールを多量に摂取すると、肝臓がアルコールの分解を優先するため、グリコーゲンの合成が後回しになることがあります。その結果として、
- 低血糖状態: 体内で糖が不足しやすくなる
- 持久力低下: 長時間のランニング時にエネルギーが足りなくなり、パフォーマンスが落ちる
こうした可能性が高まることが指摘されています。
3-3. 睡眠の質の低下
運動を頑張っている方にとって、睡眠はとても大切です。アルコールを飲むと、一見眠りやすいように感じる場合がありますが、実は睡眠構造が乱れることが多いと言われています(参考: Sleep Medicine Reviews)。
- 浅い眠りが増える: アルコールによって、一時的には寝付きがよくなる人もいますが、後半の睡眠サイクルが浅くなりやすい。
- 成長ホルモンの分泌が減る可能性: 深い睡眠時に多く分泌される成長ホルモンは、筋肉の修復や免疫機能の維持に重要です。アルコールによって深い眠りが阻害されると、回復が遅れる恐れがあります。
3-4. 疲労感・集中力への影響
アルコール摂取後は一時的にリラックスできるものの、翌日の疲労感や集中力の低下につながることが少なくありません。ランニングの際にフォームが乱れたり、足元の路面状況に対する注意力が散漫になったりすることで、ケガのリスクが高まる可能性もあります。
4. お酒がランナーに与える影響
ここでは、前章までの情報をさらにランナー向けに具体化して解説します。
4-1. 持久力とパフォーマンス
持久力が求められるランナーにとって、脱水やグリコーゲン不足は大敵です。アルコールの利尿作用やエネルギー供給への悪影響によって、翌日のランニングや大会本番にパフォーマンス低下が生じることがあります。
4-2. ケガのリスク増加
走る動作は身体のバランスやフォームが非常に重要です。アルコールによる中枢神経の抑制は、バランス感覚や判断力の低下を招きます。飲酒直後はもちろん、アルコールが分解しきれず身体に残っている状態が続くと、不注意や踏み込みのズレによる足首や膝、腰などへの負担が増し、ケガのリスクが高まる可能性があります。
4-3. 大会前の注意点
マラソンや駅伝、その他レースに出場するランナーは、特に以下の点に留意が必要です。
- 大会直前はアルコールを控える: 体内の水分や栄養バランスを最適化し、最高のコンディションでスタートラインに立つため。
- 大会前日は飲まないか、最小限に抑える: 翌日の睡眠の質や早起きにも影響するため、極力控えることが賢明です。
5. メリットとデメリットの整理
ここで、ランナーがお酒と付き合ううえで考えられるメリットとデメリットをまとめましょう。
5-1. メリット
- リラックス効果・ストレス解消
適度な飲酒は、ストレスの多い現代社会において気分をほぐす手段の一つとして有用です。ランニング後に仲間と軽く乾杯することでコミュニケーションが円滑になるなどの面もあります。 - 飲酒文化を楽しむ
ワインや日本酒、クラフトビールなど、お酒の味わいや文化を楽しむことで生活の楽しみが増すケースもあります。ランニングと同様、「楽しむこと」は生活の質を高める重要な要素です。 - 心血管系へのポジティブな影響の可能性
一部の研究では、赤ワインなどに含まれるポリフェノールが心臓血管系の健康に良い影響を与える可能性が指摘されています。ただし、これはあくまで「適量」に限った話であり、過度な飲酒は逆効果です。
5-2. デメリット
- 筋肉の回復阻害・持久力低下
筋タンパク合成の阻害やグリコーゲン合成の低下は、長期的に見れば走力の伸びを妨げる要因となります。 - 脱水・ケガのリスク増加
アルコールの利尿作用による脱水や、中枢神経への影響によるバランス感覚の低下などが挙げられます。 - 睡眠の質の低下
深い眠りを得にくくなり、結果的に身体の回復力や免疫力が下がる可能性が高まります。 - 生活習慣病のリスク
肝機能障害や高血圧、心筋梗塞などに代表される生活習慣病のリスク増。ランナーでも、アルコール摂取量次第ではこれらのリスクは否定できません。
6. ランナーのアルコールとの付き合い方(結論)
最後に、以上の情報を踏まえたうえでの結論をまとめます。
6-1. 適量を守ることが最重要
適度な飲酒であれば、リラックス効果や社交性などを得られますが、大量・長期飲酒による弊害は明白です。一般的に、「節度ある適度な飲酒」として、ビール中瓶1本(約500ml)程度、またはワイン1杯(150ml)程度が一つの目安とされています(参考: 厚生労働省 “健康日本21” など)。ただし、この量でも個人差が大きいため、自分の体質や翌日の予定などを考慮したうえでコントロールすることが大切です。
6-2. トレーニング直後の過度な飲酒は避ける
筋肉の回復が最も活発になる運動直後や就寝前にアルコールを大量摂取すると、筋肉の合成反応が阻害されやすくなります。せっかくのトレーニング効果を減らさないためにも、運動直後から数時間は特に慎重になりましょう。
6-3. 睡眠時間の確保と水分補給の工夫
アルコールで脱水状態になりやすいため、飲みながらも同量以上の水を飲むなどの工夫をしておくとよいです。また、飲酒した日にしっかりと睡眠時間を確保できるかどうかも重要なポイントになります。睡眠が不足すると、翌日のパフォーマンスだけでなく、免疫力や気分の安定にも影響が出てきます。
6-4. 大会や重要なトレーニング前は控える
レースやハードな練習の前日は、できるだけお酒を控えることをおすすめします。特にフルマラソンなど長時間の運動が要求される種目では、水分やグリコーゲンを十分に蓄えておく必要があります。直前に飲酒してしまうと、体内のエネルギー貯蔵量や睡眠の質に影響が出るため、万全の状態でスタートできない可能性があります。
6-5. 飲酒以外のストレスマネジメント
リラックスやストレス解消の手段は、何もお酒だけではありません。ストレッチやヨガ、軽い呼吸法、入浴、読書など、自分に合った方法でリラックスできる時間を確保しましょう。ランニングそのものもストレス解消効果がありますが、「走ったあと、さらにお酒でもストレスを発散する」という二重構造にならないよう、意識して多角的なリラックス法を身につけることが大切です。
7. まとめ
「ランナーとアルコールの関係」について、身体への影響、運動・トレーニング面での影響、そしてランナー目線での注意点やメリット・デメリットをお伝えしてきました。要点を振り返ると、次のようになります。
- アルコールは中枢神経を抑制し、利尿作用で脱水を招きやすい
- 筋タンパク合成やグリコーゲン合成を阻害し、パフォーマンス低下につながる可能性
- 適量ならばリラックス効果やコミュニケーションの活性化などのメリットもある
- 大量・長期飲酒は健康リスクを高め、ランナーにとっても大きなデメリット
- 大会やハードなトレーニング前は控えめにし、睡眠や栄養状態を最優先に
ランニングを楽しむためには、まず健康を維持することが不可欠です。そのためにも、アルコールとの付き合い方を工夫し、必要に応じて控えることが重要です。今日の内容が、皆さんのランニングライフや健康管理に少しでもお役に立てば幸いです。
動画で学びたい方はこちらから
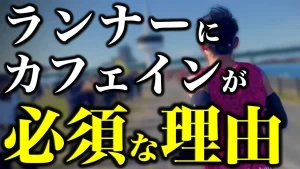


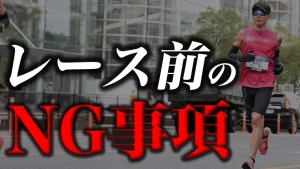
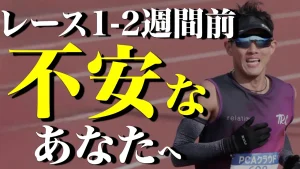
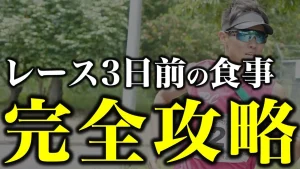
コメント